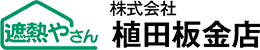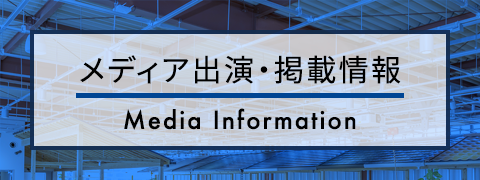職場で熱中症の発生時に問われる企業の責任とは?予防策についても紹介

従業員が職場で熱中症を発症した際に、企業が法的責任を負う可能性があります。
本記事では、職場で熱中症が発生した際に企業が問われる責任や職場でできる具体的な熱中症対策について解説します。
企業のリスクを最小限に抑え、従業員の健康と安全を守るための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
職場で熱中症が発生した際に責任が問われる理由

職場における熱中症の事故も年々増加傾向にあり、令和4〜5年の死亡災害が2年連続で30人レベルと深刻な事態となっています。
また、令和2〜5年に発生した熱中症による死亡災害では、初期症状の放置や対応の遅れが多く見られました。
こうした背景から、2025年6月に労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が企業の責務として明文化されました。
そのため、企業には以下の3つの取り組みが求められています。
・報告体制の整備
・熱中症発生時の対応手順の作成
・関係者への周知・教育
WBGT値が28℃以上または気温が31℃以上の環境下で、連続1時間以上または1日合計4時間を超える作業が対象です。
WBGTとは、湿度や日射・輻射、気温を取り入れた暑熱環境の危険度を評価する指標です。
企業には、労働安全衛生法に基づき従業員の健康と安全を守る責任があります。
気温管理の不備や水分補給・休憩の確保が不十分だった場合、企業が法的責任を問われる可能性があるため、早急な対策が求められます。
職場での熱中症対策を怠った場合に問われる企業の責任

・損害賠償請求に対する責任
・労働基準監督署の監督指導に対する責任
・罰則に対する責任
・社会的信用に関する責任
法的・行政上・社会的観点から考えられる主な4つの責任について解説します。
損害賠償請求に対する責任
従業員が熱中症を発症し、安全配慮義務違反と認定された場合、企業に対して損害賠償請求が行われる可能性があります。
労災保険が給付されたとしても、慰謝料といった労災保険の補償されない損害まで請求される場合もあります。
従業員との示談交渉が難航した場合、時間を取られるだけでなく裁判にも発展しかねません。
さらに、請求される損害賠償の金額によっては、企業の経営に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
労災保険が給付されたとしても、慰謝料といった労災保険の補償されない損害まで請求される場合もあります。
従業員との示談交渉が難航した場合、時間を取られるだけでなく裁判にも発展しかねません。
さらに、請求される損害賠償の金額によっては、企業の経営に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
労働基準監督署の監督指導に対する責任
熱中症による労災が発生し、企業側に管理体制の不備や法令違反があったと判断されると、労働基準監督署から監督指導を受ける場合があります。
指導を受けた場合は内容に応じて是正や改善を行い、労働基準監督署に報告をすることが求められます。
危険性の高い状況と判断されると、工場や作業の一部停止などの行政処分にもつながるため、責任を問われる前に熱中症対策を講じましょう。
指導を受けた場合は内容に応じて是正や改善を行い、労働基準監督署に報告をすることが求められます。
危険性の高い状況と判断されると、工場や作業の一部停止などの行政処分にもつながるため、責任を問われる前に熱中症対策を講じましょう。
罰則に対する責任
労働安全衛生法では、熱中症などの健康障害を防ぐため、企業に必要な措置を講じる義務が課されています。
違反した場合、企業は罰則の対象となる可能性があります。
罰則は個人だけでなく法人にも適用されるため、企業として従業員の健康を守る責任を果たすことが重要です。
違反した場合、企業は罰則の対象となる可能性があります。
罰則は個人だけでなく法人にも適用されるため、企業として従業員の健康を守る責任を果たすことが重要です。
社会的信用に関する責任
熱中症による重大事故が発生した場合、マスコミやSNSを通じて企業への批判が広がるリスクが生じます。
「熱中症対策を怠っていた」「作業環境に問題があった」といった印象が定着すると、企業の信用が一気に低下する可能性があります。
新卒や中途の採用が難航する、既存社員の離職率が高まるなど長期的な人材確保にも深刻な影響を及ぼしかねません。
「熱中症対策を怠っていた」「作業環境に問題があった」といった印象が定着すると、企業の信用が一気に低下する可能性があります。
新卒や中途の採用が難航する、既存社員の離職率が高まるなど長期的な人材確保にも深刻な影響を及ぼしかねません。
企業に求められる職場での熱中症対策

・報告体制の整備
・実施手順の作成
・関係者に周知
それぞれの対策について紹介します。
報告体制の整備
いち早く従業員の体調の異変を察知するためには、報告体制の明確化が重要です。
熱中症の初期症状であるめまいや吐き気、けいれんなどを見逃すと、重症化につながる恐れがあります。
従業員本人や周囲が異変に気づいた際、「誰に・どのように」報告するかをルールとして定め、周知しておくことが必要です。
熱中症の初期症状であるめまいや吐き気、けいれんなどを見逃すと、重症化につながる恐れがあります。
従業員本人や周囲が異変に気づいた際、「誰に・どのように」報告するかをルールとして定め、周知しておくことが必要です。
実施手順の作成
万が一熱中症が疑われる状況が発生した場合に備え、企業は対応手順を明確にしておく必要があります。
誰が何をすべきかが明確になっていれば、職場でも冷静な判断と迅速な処置が可能です。
手順には、作業の即時中断や冷房の効いた休憩所や日陰への避難、水分や塩分の補給、体の冷却、必要に応じた医療機関への搬送などが含まれます。
緊急連絡網の整備や医療機関の連絡先・住所の共有も忘れてはいけません。
こうした対応フローは、現場の実情に応じて柔軟に設計することが求められます。
誰が何をすべきかが明確になっていれば、職場でも冷静な判断と迅速な処置が可能です。
手順には、作業の即時中断や冷房の効いた休憩所や日陰への避難、水分や塩分の補給、体の冷却、必要に応じた医療機関への搬送などが含まれます。
緊急連絡網の整備や医療機関の連絡先・住所の共有も忘れてはいけません。
こうした対応フローは、現場の実情に応じて柔軟に設計することが求められます。
関係者に周知
せっかく整えた報告体制や手順も職場に浸透していなければ、十分に効果が発揮されません。
従業員への周知方法としては、朝礼や定例会議での説明、掲示物による案内、チェックリストや冊子の配布などが有効です。
特に外国人労働者が多い職場では、多言語対応の資料や図解・ピクトグラムの活用など、誰にでも伝わるような工夫が求められます。
理解度を高めるには、定期的な訓練やロールプレイなど実践的な熱中症に関する教育の導入も検討しましょう。
従業員への周知方法としては、朝礼や定例会議での説明、掲示物による案内、チェックリストや冊子の配布などが有効です。
特に外国人労働者が多い職場では、多言語対応の資料や図解・ピクトグラムの活用など、誰にでも伝わるような工夫が求められます。
理解度を高めるには、定期的な訓練やロールプレイなど実践的な熱中症に関する教育の導入も検討しましょう。
責任を問われる前に職場で取り組みたい熱中症の予防策

・遮熱や断熱対策の導入
・水分や塩分のこまめな補給
・作業スケジュールの見直し
・暑さ対策グッズの活用
・健康チェックや巡視体制の導入
・従業員への教育
それぞれの予防策を紹介します。
遮熱や断熱対策の導入
工場や倉庫などの屋内作業場では、遮熱・断熱対策により室温の上昇を抑えることが可能です。
遮熱は太陽光を反射させて建物への熱の侵入を防ぎ、断熱は熱の伝達を遅らせる働きを持っています。
遮熱・断熱対策を講じることで、WBGT値の上昇を抑え、熱中症リスクを根本から軽減する効果が期待できます。
とくに有効なのは、温度上昇の主な要因となっている太陽光による熱の侵入を抑える遮熱です。
遮熱やさん(運営:植田板金店)では、アルミニウムやポリエチレンを使用した遮熱材「シャネリア」を用いた工事が可能です。
シャネリアは輻射熱を約97%カットする仕様で、作業環境の暑さを効果的に和らげます。
シャネリアの詳細はこちら
遮熱は太陽光を反射させて建物への熱の侵入を防ぎ、断熱は熱の伝達を遅らせる働きを持っています。
遮熱・断熱対策を講じることで、WBGT値の上昇を抑え、熱中症リスクを根本から軽減する効果が期待できます。
とくに有効なのは、温度上昇の主な要因となっている太陽光による熱の侵入を抑える遮熱です。
遮熱やさん(運営:植田板金店)では、アルミニウムやポリエチレンを使用した遮熱材「シャネリア」を用いた工事が可能です。
シャネリアは輻射熱を約97%カットする仕様で、作業環境の暑さを効果的に和らげます。
シャネリアの詳細はこちら
水分や塩分のこまめな補給
暑さが厳しい環境下で安全に作業を行うには、水分と塩分の補給が欠かせません。
経口補水液や塩分入りタブレットなどを職場に常備し、自由に摂取するように従業員に共有しましょう。
従業員が自発的に予防行動を取れるような職場の雰囲気づくりが、熱中症の発生防止につながります。
経口補水液や塩分入りタブレットなどを職場に常備し、自由に摂取するように従業員に共有しましょう。
従業員が自発的に予防行動を取れるような職場の雰囲気づくりが、熱中症の発生防止につながります。
作業スケジュールの見直し
気温が高くなる時間帯を避けて作業を行ったり、連続作業を避けたりするなど天候や気温に応じたスケジューリングが大切です。
また、空調の効いた休憩所や日陰スペースを設け、こまめに休憩できるような労働環境を整備しましょう。
また、空調の効いた休憩所や日陰スペースを設け、こまめに休憩できるような労働環境を整備しましょう。
暑さ対策グッズの活用
通気性や吸汗速乾性に優れた素材の作業服を採用することで、長袖でも熱がこもりにくくなります。
ファン付き作業着や冷却ベストなど、身体を冷やせるウェアの導入も効果的です。
さらに、ネッククーラーや冷却タオルなどのグッズを併用すれば、体感温度をより一層下げられます。
▼関連記事
工場の暑さ対策に有効な設備やグッズを紹介!個人・現場の対応方法も解説
ファン付き作業着や冷却ベストなど、身体を冷やせるウェアの導入も効果的です。
さらに、ネッククーラーや冷却タオルなどのグッズを併用すれば、体感温度をより一層下げられます。
▼関連記事
工場の暑さ対策に有効な設備やグッズを紹介!個人・現場の対応方法も解説
健康チェックや巡視体制の導入
作業開始前には、従業員の頭痛や倦怠感などがないか健康チェックを実施しましょう。
体調に不安がある従業員を早期に把握できれば、事故の予防につながります。
管理者や衛生担当者が定期的に現場を巡視し、顔色や動き、発汗状況などの変化を見逃さないことも重要です。
「異変があったらすぐ報告して良い」という安心感のある職場づくりも欠かせません。
体調に不安がある従業員を早期に把握できれば、事故の予防につながります。
管理者や衛生担当者が定期的に現場を巡視し、顔色や動き、発汗状況などの変化を見逃さないことも重要です。
「異変があったらすぐ報告して良い」という安心感のある職場づくりも欠かせません。
従業員への教育
企業は、熱中症対策について定期的かつ継続的な教育を全従業員に行うことが求められます。
熱中症の症状や対応方法については、動画教材や研修会などを活用して周知を図りましょう。
また、緊急時の冷却処置や救急搬送に関する応急手当の訓練も定期的に実施し、万が一の事態に備えることも大切です。
熱中症の症状や対応方法については、動画教材や研修会などを活用して周知を図りましょう。
また、緊急時の冷却処置や救急搬送に関する応急手当の訓練も定期的に実施し、万が一の事態に備えることも大切です。
責任を問われる前に職場で熱中症対策を実施して従業員の安全を守ろう

職場で熱中症対策を怠ると、従業員の体調不良や重大な事故につながるだけでなく、法令によって責任を問われる可能性があります。
従業員の健康を守り、企業の信頼と継続的な事業運営にもつなげるためにも事前の対策が重要です。
責任を問われる前に、職場での熱中症対策を進めていきましょう。
▼関連記事
夏に工場が暑くなる原因と対策を解説!設備や個人向けアイテムなどを紹介