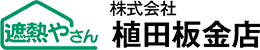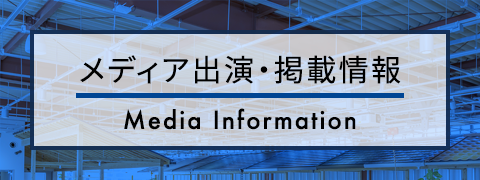寒すぎる職場は法令違反?罰則やデメリット、対策例などを解説

「法令違反になった場合、罰則はあるのだろうか」
職場が寒すぎる場合、従業員の健康状態の悪化や作業効率の低下といったリスクが発生するおそれがあります。
職場の寒さが気になる方の中には、自社の環境が法令違反になるのではないかと、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では寒すぎる職場が法令違反になるのかどうかについて解説します。
職場の温度管理に関わる法令の紹介や罰則の有無、寒さを改善するための対策なども紹介します。
寒すぎる職場が法令違反になるかお悩みの担当者の方は、ぜひご覧ください。
寒すぎる職場は法令違反になる可能性がある

労働安全衛生法では、事業者に低温な環境などによって従業員が健康被害にならないよう、措置をとる義務が課せられています。
寒すぎる環境を改善するための措置を行わず、従業員の健康が損なわれた場合は法令違反になりかねません。
寒すぎる職場に関連する法令

・工場や店舗が対象になる「労働安全衛生規則」
・事務所・オフィスに適用される「事務所衛生基準規則」
法令の内容や罰則の有無などについて解説するので、ぜひご覧ください。
工場や店舗が対象になる「労働安全衛生規則」
工場や店舗などには、労働安全衛生法に基づいて定められた「労働安全衛生規則」が適用されます。
温度や湿度については、適当な温湿度調節の措置を講じなければならないとされており、労働者を保護する措置が必要です。
たとえば、以下のようなケースでは何らかの対策が必要と考えられます。
・冷凍倉庫で作業する従業員に、十分な防寒着を支給していない
・寒さで手がかじかみ、作業でミスが多発している
作業環境や作業内容に即して、労働者が安全に働ける環境の整備が必要です。
規則に違反していると判断された場合は罰則があります。
罰則は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条)が課せられます。
自社工場が寒すぎると懸念される場合は、早急に対策を行いましょう。
温度や湿度については、適当な温湿度調節の措置を講じなければならないとされており、労働者を保護する措置が必要です。
たとえば、以下のようなケースでは何らかの対策が必要と考えられます。
・冷凍倉庫で作業する従業員に、十分な防寒着を支給していない
・寒さで手がかじかみ、作業でミスが多発している
作業環境や作業内容に即して、労働者が安全に働ける環境の整備が必要です。
規則に違反していると判断された場合は罰則があります。
罰則は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条)が課せられます。
自社工場が寒すぎると懸念される場合は、早急に対策を行いましょう。
事務所・オフィスに適用される「事務所衛生基準規則」
事務所衛生基準規則は、事務所を対象にした規則です。
事務所は一般的なオフィスを指し、多くの工場や店舗などは事務所に含まれません。
職場の衛生基準については、労働安全衛生法に基づいて定められた「事務所衛生基準規則」が適用されます。
事務所衛生基準規則では、事業者が労働者の健康維持のために講じるべき措置が定められており、温度についても基準があります。
事務所の温度湿度について定められている基準は以下のとおりです。
・努力義務:室温が18度以上28度以下および相対湿度が40%以上70%以下(第5条)
・義務:室温が10度以下の場合は、温度調節の措置を講じる(第4条)
また、冷房を使用する場合は室温を外気温より著しく低くしてはならないという項目もあります。
第4条に違反すると労働安全衛生法第23条(事業者の講ずべき措置等)の違反に該当し、罰則が適用されるため、注意が必要です。
罰則は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条)が課せられます。
一方、第5条は努力義務のため、違反しても罰則はありません。
しかし、従業員の健康や業務の生産性などに関わるため、適切な温度管理が求められます。
事務所は一般的なオフィスを指し、多くの工場や店舗などは事務所に含まれません。
職場の衛生基準については、労働安全衛生法に基づいて定められた「事務所衛生基準規則」が適用されます。
事務所衛生基準規則では、事業者が労働者の健康維持のために講じるべき措置が定められており、温度についても基準があります。
事務所の温度湿度について定められている基準は以下のとおりです。
・努力義務:室温が18度以上28度以下および相対湿度が40%以上70%以下(第5条)
・義務:室温が10度以下の場合は、温度調節の措置を講じる(第4条)
また、冷房を使用する場合は室温を外気温より著しく低くしてはならないという項目もあります。
第4条に違反すると労働安全衛生法第23条(事業者の講ずべき措置等)の違反に該当し、罰則が適用されるため、注意が必要です。
罰則は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条)が課せられます。
一方、第5条は努力義務のため、違反しても罰則はありません。
しかし、従業員の健康や業務の生産性などに関わるため、適切な温度管理が求められます。
法令違反になりかねないほど寒すぎる職場のデメリット

・従業員の健康状態の悪化
・作業効率や生産性の低下
それぞれ詳しく解説するので、どのような弊害があるのか、把握しましょう。
従業員の健康状態の悪化
職場が寒すぎると従業員の健康状態が悪化する可能性が高くなります。
たとえば体の冷えや自律神経の乱れ、免疫力の低下などを招き、体調不良につながります。
特に冬は空気が乾燥しており、風邪やインフルエンザなどの感染症が流行しやすい時期です。
社内で風邪やインフルエンザが広がり、欠勤する従業員が増加すると、生産活動に支障をきたしてしまう可能性があります。
従業員の健康を守り、安定した生産活動を実現するためにも、寒さ対策は重要です。
たとえば体の冷えや自律神経の乱れ、免疫力の低下などを招き、体調不良につながります。
特に冬は空気が乾燥しており、風邪やインフルエンザなどの感染症が流行しやすい時期です。
社内で風邪やインフルエンザが広がり、欠勤する従業員が増加すると、生産活動に支障をきたしてしまう可能性があります。
従業員の健康を守り、安定した生産活動を実現するためにも、寒さ対策は重要です。
作業効率や生産性の低下
工場などの職場が寒すぎると、作業効率や生産性の低下といった弊害も発生しかねません。
職場が寒すぎると、集中力の低下や手がかじかむなどの弊害が生じ、作業が思うように進まないおそれがあります。
注意力が散漫、体が思うように動かないといった状態だと、ミスが増加して作業効率が低下してしまいます。
怪我や大きな事故につながると、業務がストップするおそれもあるため、寒さによる弊害を予防する対策が必要です。
寒さ対策には一定のコストが伴いますが、作業効率や生産性を維持するためにも実施しましょう。
職場が寒すぎると、集中力の低下や手がかじかむなどの弊害が生じ、作業が思うように進まないおそれがあります。
注意力が散漫、体が思うように動かないといった状態だと、ミスが増加して作業効率が低下してしまいます。
怪我や大きな事故につながると、業務がストップするおそれもあるため、寒さによる弊害を予防する対策が必要です。
寒さ対策には一定のコストが伴いますが、作業効率や生産性を維持するためにも実施しましょう。
法令違反にならないために寒すぎる職場で実施できる対策

おもな対策としては、下記が挙げられます。
・遮熱工事や断熱工事
・暖房器具の設置
・サーキュレーターの活用
・加湿器の活用
それぞれ詳しく紹介するので、職場に取り入れられるものがないか、ご確認ください。
遮熱工事や断熱工事
職場の寒さ対策には遮熱工事や断熱工事がおすすめです。
遮熱工事は赤外線などによって伝わる輻射熱を反射させるため、外へ逃げようとする熱を室内に留める効果が期待できます。
一方の断熱工事には熱の移動を抑制する効果があり、暖房で温められた熱が外へ逃げにくくなるので、室温の安定化につながります。
遮熱工事や断熱工事によって空調効率がアップすれば、設定温度に達するまでに要するエネルギーの節約が可能です。
使うエネルギーが少ない分、光熱費の削減効果も期待できます。
夏の暑さ対策としても効果的なので、一度検討するのがおすすめです。
▼関連記事
遮熱材と断熱材の違いとは?伝わる熱の種類や具体的な商品についても解説
遮熱工事は赤外線などによって伝わる輻射熱を反射させるため、外へ逃げようとする熱を室内に留める効果が期待できます。
一方の断熱工事には熱の移動を抑制する効果があり、暖房で温められた熱が外へ逃げにくくなるので、室温の安定化につながります。
遮熱工事や断熱工事によって空調効率がアップすれば、設定温度に達するまでに要するエネルギーの節約が可能です。
使うエネルギーが少ない分、光熱費の削減効果も期待できます。
夏の暑さ対策としても効果的なので、一度検討するのがおすすめです。
▼関連記事
遮熱材と断熱材の違いとは?伝わる熱の種類や具体的な商品についても解説
暖房器具の設置
空調を稼働しても職場全体が暖まりにくい場合は、石油ストーブや遠赤外線ヒーターなどの暖房器具の設置が有効です。
電源や灯油を用意すれば導入できる暖房器具も多く、手軽に設置できます。
ただし、燃焼式の暖房は酸素不足による一酸化炭素中毒の危険があるため、定期的な換気が必要です。
電源や灯油を用意すれば導入できる暖房器具も多く、手軽に設置できます。
ただし、燃焼式の暖房は酸素不足による一酸化炭素中毒の危険があるため、定期的な換気が必要です。
サーキュレーターの活用
サーキュレーターの導入も、寒さ対策として有効です。
暖かい空気は室内の上部に滞留する性質があるため、いくら暖房を稼働させても、床付近の温度が上がりにくい傾向があります。
そこでサーキュレーターで上部に滞留した暖かい空気を循環させると、部屋全体の温度差がなくなり、効率的に暖かくなります。
エアコンの稼働時間が短くなり、設定温度を上げすぎる必要もないため、節電にも効果的です。
サーキュレーターは、比較的少ないコストで導入できるのもメリットです。
暖かい空気は室内の上部に滞留する性質があるため、いくら暖房を稼働させても、床付近の温度が上がりにくい傾向があります。
そこでサーキュレーターで上部に滞留した暖かい空気を循環させると、部屋全体の温度差がなくなり、効率的に暖かくなります。
エアコンの稼働時間が短くなり、設定温度を上げすぎる必要もないため、節電にも効果的です。
サーキュレーターは、比較的少ないコストで導入できるのもメリットです。
加湿器の活用
冬は空気が乾燥しやすい季節です。
乾燥した空気が肌から水分を奪う際の気化熱によって、体感温度が下がる場合があります。
体感温度の低下を防ぐには、加湿器の導入がおすすめです。
湿度を適正に保てば体感温度の低下を抑える効果が期待できるため、必要以上に設定温度を上げる必要がなくなり、省エネにつながります。
また、ウイルスによっては加湿を行うと空気中に漂う量が増えにくくなる傾向があるため、感染症予防の効果も期待できます。
乾燥した空気が肌から水分を奪う際の気化熱によって、体感温度が下がる場合があります。
体感温度の低下を防ぐには、加湿器の導入がおすすめです。
湿度を適正に保てば体感温度の低下を抑える効果が期待できるため、必要以上に設定温度を上げる必要がなくなり、省エネにつながります。
また、ウイルスによっては加湿を行うと空気中に漂う量が増えにくくなる傾向があるため、感染症予防の効果も期待できます。
寒すぎる職場で対策を実施する際の注意点

暖房を稼働しても、職場全体の温度を一定に維持できるわけではありません。
室温は外気や人口密度、機器から発せられる熱などに影響を受けやすく、暖房の設定温度と一致しない場合があります。
快適な温度に保つには、職場に温度計を設置し、定期的な室温の確認が必要です。
また、人によって体感温度が異なる点にも注意しましょう。
法令が定める基準を満たしていても、人によっては寒すぎると感じる場合があります。
たとえば、男性よりも筋肉量が少ない傾向がある女性や、加齢に伴い筋肉が衰える高齢者などは、体感温度が低くなりがちです。
法令の基準を満たしていても、寒く感じる従業員がいる場合は、今後の対策などを従業員個人と話し合う必要があります。
寒さによる工場の法令リスクを低減するなら遮熱がおすすめ

暖房や機械から発せられる熱を反射させて、室温が下がりにくくなる効果が見込めます。
さらに、暖房効率の向上による工場全体のコストの削減効果も期待できます。
遮熱やさん(運営:植田板金店)は、工場で実施できる様々な遮熱工事に対応可能です。
法令違反にならないための寒さ対策として遮熱に興味がある方は、気軽にご相談ください。
▼関連記事
工場の寒さ対策は何がいい?原因やおすすめの対処法なども紹介
工場が暑いのは違法になる?夏場の暑さ対策方法について解説