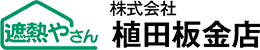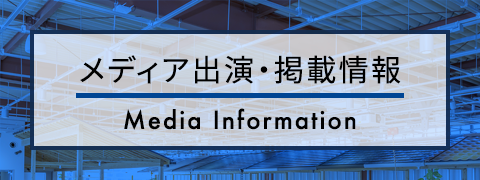工場経営者の事業承継における節税対策!知らなきゃ損するお金の話
2024.11.11
目次 【表示】 【非表示】

事業承継をする際、相続税やその他の税を節約したい方は多いと思います。
税金は、知識があるかないかで大きく金額が変わりかねません。
事業承継に関わる節税を考えている工場経営者向けに、知らなきゃ損する節税対策をご紹介いたします。
ぜひ最後までチェックして、無駄なお金を支払わないようにしましょう。
事業承継で発生する税金の例

・相続税
・贈与税
・所得税
あくまで一例のため、必ずしもかかるとは限りません。
反対に別の税金が発生する場合もあるため、詳しいことは税理士や国税庁に問い合わせる必要があります。
相続税
相続税とは現経営者が亡くなった際、会社を引き継いだときにかかる税金のことです。
相続税は主に下記の流れで算出します。
・基礎控除額の計算
・課税遺産総額の計算
・法定相続分に応じた課税額を計算
・相続税総額を各相続人で分割
・税額控除の適用
基礎控除は相続税の対象となる財産の総額から差し引かれる金額です。
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。
基礎控除額を差し引いたあとの遺産額が課税遺産総額です。
次に課税遺産総額を法定相続分に応じて分けたと仮定し、それぞれにかかる課税額を計算します。
日本の相続税率は累進課税方式です。
所得や財産の増加にともない、税率が段階的に高くなる課税方式を採用しています。
たとえば1,000万円以下は10%、5,000万円超えから1億円以下は30%、6億円超えなら55%です。
各相続人の実際の相続税額は「課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分」で算出します。
最後に、配偶者控除や未成年控除などを差し引いて最終的な税額を決定します。
相続税は基礎控除額が設定されているため、基準を下回るなら相続税は発生しません。
相続税は主に下記の流れで算出します。
・基礎控除額の計算
・課税遺産総額の計算
・法定相続分に応じた課税額を計算
・相続税総額を各相続人で分割
・税額控除の適用
基礎控除は相続税の対象となる財産の総額から差し引かれる金額です。
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。
基礎控除額を差し引いたあとの遺産額が課税遺産総額です。
次に課税遺産総額を法定相続分に応じて分けたと仮定し、それぞれにかかる課税額を計算します。
日本の相続税率は累進課税方式です。
所得や財産の増加にともない、税率が段階的に高くなる課税方式を採用しています。
たとえば1,000万円以下は10%、5,000万円超えから1億円以下は30%、6億円超えなら55%です。
各相続人の実際の相続税額は「課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分」で算出します。
最後に、配偶者控除や未成年控除などを差し引いて最終的な税額を決定します。
相続税は基礎控除額が設定されているため、基準を下回るなら相続税は発生しません。
贈与税
贈与税とは、生前に現経営者が会社を譲渡したときにかかる税金のことです。
贈与税には2種類あります。
・一般贈与財産
・特例贈与財産
一般贈与財産は兄弟間や夫婦間、親から未成年の子への贈与が対象です。
特例贈与財産は父母や祖父母など直系尊属からの贈与に使用します。
贈与税の主な計算方法は下記のとおりです。
・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与でもらった財産の価額を合計する
・合計額から基礎控除額110万円を差し引く
・残りの金額に税率を乗じて税額を計算する
一般贈与財産の場合は累進課税が適用され、贈与額が大きくなるほど税率も高くなります。
たとえば600万円以下なら30%、1,500万円超〜3,000万円以下なら50%です。
一方、特例贈与財産の税率は特例税率のため一般税率より低い特徴があります。
600万円以下なら20%、1,500万円超〜3,000万円以下なら45%と税負担が軽くなります。
贈与税には2種類あります。
・一般贈与財産
・特例贈与財産
一般贈与財産は兄弟間や夫婦間、親から未成年の子への贈与が対象です。
特例贈与財産は父母や祖父母など直系尊属からの贈与に使用します。
贈与税の主な計算方法は下記のとおりです。
・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与でもらった財産の価額を合計する
・合計額から基礎控除額110万円を差し引く
・残りの金額に税率を乗じて税額を計算する
一般贈与財産の場合は累進課税が適用され、贈与額が大きくなるほど税率も高くなります。
たとえば600万円以下なら30%、1,500万円超〜3,000万円以下なら50%です。
一方、特例贈与財産の税率は特例税率のため一般税率より低い特徴があります。
600万円以下なら20%、1,500万円超〜3,000万円以下なら45%と税負担が軽くなります。
所得税
所得税は現経営者が払う税金です。
事業承継のほか株や資産を売却した際、得た利益に対して所得税を払う必要があります。
たとえば、土地や建物を譲渡した場合にかかる所得税は譲渡所得です。
「収入金額-( 取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。
収入金額は土地や建物を譲渡したときに、対価として買主から受け取る金銭です。
売った土地や建物の購入代金、設備費や改良費などの取得費と、売るために直接かかった譲渡費用の合計を収入金額から差し引きます。
さらに、特別控除額を差し引くと課税譲渡所得金額を算出できます。
特別控除額は一定の要件を満たす場合に適用され、収用等により土地建物を譲渡した場合は5,000万円です。
譲渡所得の税額は給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が適用されます。
・長期譲渡所得:課税長期譲渡所得金額×15%
・短期譲渡所得:課税短期譲渡所得金額×30%
土地や建物の売却は一時的に大きな所得になるため、分離課税制度により税金の負担軽減を図っています。
事業承継のほか株や資産を売却した際、得た利益に対して所得税を払う必要があります。
たとえば、土地や建物を譲渡した場合にかかる所得税は譲渡所得です。
「収入金額-( 取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。
収入金額は土地や建物を譲渡したときに、対価として買主から受け取る金銭です。
売った土地や建物の購入代金、設備費や改良費などの取得費と、売るために直接かかった譲渡費用の合計を収入金額から差し引きます。
さらに、特別控除額を差し引くと課税譲渡所得金額を算出できます。
特別控除額は一定の要件を満たす場合に適用され、収用等により土地建物を譲渡した場合は5,000万円です。
譲渡所得の税額は給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が適用されます。
・長期譲渡所得:課税長期譲渡所得金額×15%
・短期譲渡所得:課税短期譲渡所得金額×30%
土地や建物の売却は一時的に大きな所得になるため、分離課税制度により税金の負担軽減を図っています。
事業承継の際に重要となる株価

自社の株価を把握するためにも、株価の算定方法を知っておきましょう。
類似業種比準
類似業種比準とは自社と事業内容や規模が似ている上場企業の株価を参考にして、株価を決める方法のことです。
主に大規模の事業承継で用いられる算定方法です。
類似業種比準価額の算定に必要な要素は3つあります。
・配当金額
・利益金額
・純資産価額
類似業種比準は上場企業の株価を基準にするため、株式市場や景気の変動が反映されます。
経済が不安定な時期だと株価評価にも影響が出やすくなります。
株価は自社の利益や配当金、純資産の金額が増加すると上昇傾向です。
自社の収益力が向上し、安定している場合は株主への利益還元が大きいと評価されるからです。
一方、利益や配当金が減少すると株価も下がる可能性があります。
主に大規模の事業承継で用いられる算定方法です。
類似業種比準価額の算定に必要な要素は3つあります。
・配当金額
・利益金額
・純資産価額
類似業種比準は上場企業の株価を基準にするため、株式市場や景気の変動が反映されます。
経済が不安定な時期だと株価評価にも影響が出やすくなります。
株価は自社の利益や配当金、純資産の金額が増加すると上昇傾向です。
自社の収益力が向上し、安定している場合は株主への利益還元が大きいと評価されるからです。
一方、利益や配当金が減少すると株価も下がる可能性があります。
純資産価額
純資産価額は自社の資産や負債を元にして、1株あたりの価値を算出する方法です。
主に中小企業が相続税の評価や事業承継の際に、自社株の価値を算出するために使用します。
資産から負債を引いた純資産額で計算するため、株価が大きく変動しにくい特徴があります。
さらに長期間経営している会社は純資産が増えやすく、株価が高くなる傾向です。
安定した株価評価をしたい中小企業にとって適した方法といえます。
主に中小企業が相続税の評価や事業承継の際に、自社株の価値を算出するために使用します。
資産から負債を引いた純資産額で計算するため、株価が大きく変動しにくい特徴があります。
さらに長期間経営している会社は純資産が増えやすく、株価が高くなる傾向です。
安定した株価評価をしたい中小企業にとって適した方法といえます。
工場経営者向けの事業承継における節税対策の例

・事業承継税制
・小規模企業共済
上記はあくまで一例で、必ずしも節税できるとは限りません。
ほかにも節税対策はあるため、詳しくは税理士や国税庁にお問い合わせください。
事業承継税制
事業承継税制とは会社の事業を後継者に引き継いだときに、本来なら支払うはずの相続税や贈与税が免除される制度のことです。
後継者がさらに次の世代に事業を引き継いだ場合に適用されます。
たとえば親から子へ会社を引き継ぐときには相続税がかかります。
しかし、子が次の世代へ事業を引き継ぐと相続税を支払わなくてすむ制度が事業承継税制です。
後継者の税負担を大幅に減らせる点が大きなメリットです。
ただし、特例措置は2027年(令和9年)12月31日までにおこなわれた贈与、または相続と期限が決められています。
免除になる期間の税金に関してはあくまで猶予されている状態です。
認定後も都道府県や税務署へ報告が必要になるデメリットもあります。
後継者がさらに次の世代に事業を引き継いだ場合に適用されます。
たとえば親から子へ会社を引き継ぐときには相続税がかかります。
しかし、子が次の世代へ事業を引き継ぐと相続税を支払わなくてすむ制度が事業承継税制です。
後継者の税負担を大幅に減らせる点が大きなメリットです。
ただし、特例措置は2027年(令和9年)12月31日までにおこなわれた贈与、または相続と期限が決められています。
免除になる期間の税金に関してはあくまで猶予されている状態です。
認定後も都道府県や税務署へ報告が必要になるデメリットもあります。
小規模企業共済
小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主などを対象とした退職金制度のひとつです。
毎月一定額のかけ金を支払うことで、経営者が退職した際や廃業するときに給付金を受け取れます。
月々のかけ金は1,000〜70,000円まで、500円単位で自由に設定できます。
満期や満額はありません。
共済金の受け取り方は一括・分割・一括と分割の併用から選択可能です。
一括受取りは退職所得扱いに、分割受取りは公的年金などの雑所得扱いになります。
退職所得は退職所得控除が、公的年金は公的年金等控除が適用されるため、税金の負担軽減に有効です。
しかし20年未満で任意解約をした場合は、受け取る共済金が元本割れするリスクがあります。
20年先まで見通すことは難しいため、期間に縛られる点はデメリットです。
毎月一定額のかけ金を支払うことで、経営者が退職した際や廃業するときに給付金を受け取れます。
月々のかけ金は1,000〜70,000円まで、500円単位で自由に設定できます。
満期や満額はありません。
共済金の受け取り方は一括・分割・一括と分割の併用から選択可能です。
一括受取りは退職所得扱いに、分割受取りは公的年金などの雑所得扱いになります。
退職所得は退職所得控除が、公的年金は公的年金等控除が適用されるため、税金の負担軽減に有効です。
しかし20年未満で任意解約をした場合は、受け取る共済金が元本割れするリスクがあります。
20年先まで見通すことは難しいため、期間に縛られる点はデメリットです。
工場の修理や暑さ対策で節税できることも

雨漏りの修繕や現状回復する屋根・外壁修理は経費にあたり、節税対策になるからです。
そもそも建物のリフォーム費用は、資本的支出と修繕費の2種類に分けられて計上されます。
資本的支出とは新たな機能を付け加え、過ごしやすくするリフォームのことです。
資産として扱われるため、すぐに経費として計上できません。
代わりに減価償却を通じて数年にわたり少しずつ経費として計上されます。
修繕費は建物の原状回復、元に戻すための費用です。
その年の経費として全額計上できるため、税金の負担減少につながります。
資本的支出は長く税金を減少でき、修繕費は即時に税金の負担を減らせるメリットがあります。
ご紹介している内容は2024年11月時点の情報であり、現在も実施可能なことを保証するものではございません。
詳細が異なることがございますため、詳しくは税理士または国税庁にお問い合わせください。
さらに、工場の遮熱対策に関しては補助金が出るケースがあります。
これから暑さ対策を検討している場合は補助金もチェックしておくことがおすすめです。
工場の暑さ対策の補助金の詳細はコチラ
植田板金店では、工場などのさまざまな熱対策の方法のご提案をしております。
熱対策でお悩みの場合はお気軽にご相談くださいませ。